テストにだってデザイン性が要るよ!?【高校非常勤講師奮闘記】

学校といえば定期テストですね。
定期テストを作成する担当は、持ち回りで決まっているようですが、
(思い返すと、私が高校生のころもそうだった)
前任者が受け持っていたクラスの授業をするということが至上課題だったからか、
さすがに、テスト作成までのお願いは回ってきませんでした。

Lukia
ただし、作成したテストの事前チェックはあります。
その際、ちょっと気になることがありました。
先生方、テストには視認性と判読性の高いフォントを使ってください
ざっくりいうと、テストのフォントが統一されていないのが気になりました。
テストを作成なさる先生方にお願いです。
定期テストには、視認性と判読性の高いフォントを使ってください。
なんなら、全教科で使用するフォントを統一してください。
授業で使うプリントはまだしも、
テストにおいて、先生の個性を出す必要はありません。
むしろそんなことをすれば、生徒たちに、(あ、誰々先生が作ったんだな)とさとられてしまいます。
定期テストでフォントを統一するべき理由
定期テストにおいて、重要視されるべき、優先されるべきことは、
公平性を保つことです。
公平性を保つには、高い匿名性が必要なのです。
今、自分が高校生だったころを思い出しました。
「今回のテスト、○○先生が作るみたいだから、難しいみたいだよ」なんて噂が流れたりしてたなぁ。と。
(だからといって、特になにか対策を講じたわけでもありませんが)
そうなると、○○先生に担当されているクラスは、授業中の先生のようすや板書などから、ある程度のヒントが得られるかもしれないから有利だ。なんて発想をする生徒がいてもおかしくないですよね。
まぁ、何十年も昔ならわかります。
パソコンはおろかワープロ(ワードプロセッサ)すらない頃は、
先生たちは手書きで定期テストの問題を作っていたのだろうと思います。
ワープロが出回ってきても、それはなかなかの高級品でしたし、
教員の人数分、学校がワープロを買うなんて発想はありませんでした。
ですから、自腹でワープロやパソコンを購入することになるので、お金をためている最中の先生は、買えるまで手書きだったでしょうし、
機械に不慣れな年配の先生は、手書きにこだわられたと思います。
また、ワープロやパソコンを購入したとしても、作成した文書を印刷するためのインクカートリッジも自腹。ということになるので、手書きじゃないプリントやテストのほうが珍しかったように思います。
ちなみに、私の高校時代の国語の先生は、自他ともに認める悪筆でした。(笑)
ですから、板書は仕方ないものの、プリントなどはワープロで作っていらっしゃいました。
その先生のお気に入りのフォントがあって、プリントも定期テストもそのフォントでお作りになるので、
あ、○○先生が作ったテストなんだな。なんてわかってしまうのでした。
潔く昔のことを棚に上げて物申す
このように、パソコンもワープロも一般的ではなかった30年以上昔ならば、
匿名性が保てないのもいたしかたないでしょう。
今の人たち(先生・生徒問わず)からは、
「自分たちのときのことは、昔だって棚にあげて…」と言われそうですが、
学校によってはICT化も進み、学校が教師だけでなく、生徒にもデジタルデバイスを貸与するようになってきたこのご時世です。
あまり個々人の経済的負担を伴わずに、デジタルデバイスを所有できるようになってきた今こそ、
匿名性の高い定期テストを作成する意義があると思います。
生徒に言い訳をさせない環境をつくる
人間誰しも心の弱い生き物です。
何かしら理由をつけて、自分が勉強しないことの言い訳をしたがります。
言い訳や屁理屈も、一応論理的思考ではありますので、人生の経験としてさせてみるのは必要だと思いますが、
同時に絶対に通らないという経験もさせる必要があると思います。
しかし、大人の私たちすべてに、そんな度量があるでしょうか。
なまじっか、ダメ元で言ってみて通った!という誤った成功体験を植えつけることは、
いいことではありません。
生徒は、そんなわけないと内心わかっていても、
自分の担当じゃない先生が作ったテストだから、その授業を受けていない自分は不利なんだと言ってみたいのです。
(こういう心理を防衛機制とか、自己正当化といいます)
言ってみて、相手がぐっと言葉に詰まれば、それは誤った成功体験となってしまいます。
ダメ元でも言ったもん勝ちだ。なんて学習させてしまえば、
次世代、次々世代は、それに輪をかけたよくない思考を学習してしまうでしょう。

Lukia
この理屈に従えば、
定期テスト作成者に担当されている生徒たちは有利なはずですが、
点数を取れなかったら、それはそれでまた屁理屈をこねるのでしょう。
くりかえしますが、大人は、子供に屁理屈をこねさせるだけの余裕や度量は持っておくべきですが、
(屁理屈にだって、教育的効果はあります)
確実に阻む状況を作ってもおくべきなんですよね。
そのフォント、判読性の高いものですか?
視認性というのは、ぱっと目に入ってくる。という意味です。
思わず目を惹かれて読んでしまう。と言い換えてもいいかもしれません。
ゴシック体などは視認性の高いフォントだといえます。
文字の線の太さが一定で、どちらかというと太めなので、ぱっと目に入ってきやすいフォントだといえます。
また、古印体とか隷書体なんてのも、ペンやえんぴつなどで書ける人は少ないので、
ぱっと目を惹くフォントといえるでしょうね。
お化け屋敷の看板だとか、古風とか中国チックな商品やサービスのポスターなどに使うとよいかと思います。
判読性というのは、読みやすさのことです。
もっというと、読んでも疲れにくいフォントということができると思います。
定期テストをはじめ、テストと名のつくものは、この判読性を意識する必要があると思います。
線が均一太い文字は、無意識で「重要なことが強調されている」と認識してしまったりします。
よどみなく読み進めるためには、読むのにそれほど力や意識を必要としない、楽なフォントが使われている必要があるのです。
ここで、たとえば、国語の先生お気に入りのフォントが、判読性ではなく、視認性の高いフォントだったとしたら、
生徒たちは本文を読むのにすごく苦労してしまい、
「もういいや。」とあきらめる子が出てくるかもしれないのです。
本文に判読性の低いフォントが使われていたことによって、戦意喪失してしまったなんて、
定期テストの精度が疑われてもしかたないと思います。
フォントだってデザインの一種だ
ポスターやチラシ、プレゼンテーションなどでは、
その訴求効果を極限まで高めるため、視認性・判読性の高いフォントを意識的に使っているようです。
デザインというと、ファッションや建築、アートの世界で用いられる用語のように思えますが、
ユニバーサルデザインという言葉が出てきたように、
人の暮らしに役立つように仕組みや様相を変容させることをデザインというようです。
生徒にストレスをかけず、持っている力を正確に適切に判断するには、
テストのフォントや、行間など、テストそのもののデザイン性にも留意するべきなのです。
整然としていて、誰が作ったのかわからない無機的なテストを作ることが、
公平性を保ち、テスト後の対応も淡々とこなせる状況を生むと考えています。
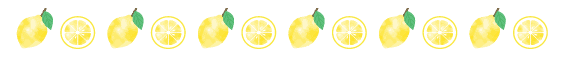 以下の記事一覧に他のボリュームのブログカードを載せています。
以下の記事一覧に他のボリュームのブログカードを載せています。
途中のボリュームからお読みになった方はこちらからどうぞ。
[subscribe2]








