フローチャートで「MECE」性を高める【持続可能なブログ更新のために】

いろんなマニュアルを作ってきた。
思い返すと、これまで、自分だけのマニュアルをたくさん作ってきました。
今後定期的に行う作業ができたとすると、
初めて作業を行った直後に必ずマニュアルを作成します。
何しろ体験が生々しいので、どんなことで困ったり、手間取ったりしたのか、
どうすればよかったのかなどが、最もよくわかっているからです。
時間をおいて、また同じことをするときに、
「あれ?これ、どうやってやるんだったっけ?」なんて
説明書を開いたり、ネット検索をしたりしたくないので、
本当に細かく、わかりやすい自分だけのマニュアルを作ります。
しかし、そのマニュアルを大いに活かすには、
何に書き留めるか。という問題をクリアせねばなりません。
買い物リストや週や月単位のタスクは、Todoアプリに。
不定期で作りたくなる料理は、レシピアプリに。
グーグルカレンダーをTodoアプリとして使っていたこともあります。
チェックリストが簡単に作れて、アラート機能もあるので、Google Keepあたりもオススメです。
「判断」で分岐するマニュアルを作るには?
しかし、上のマニュアルやアプリは、ある意味「迷いがない」場合は役立ちますが、
「判断」によって、次の作業が分岐する場合は、うまく機能しないことになります。
今回、ブログを書くためのルールを見直したことで、
その手順も見直せたのですが、そこで「判断」という分岐点が生じました。
上記のアプリなどは使えないので、マニュアルを紙に書くことになるのですが、
従来の書き方だと、どんなにていねいに書いても、時間が経つと見直してもよくわからなくなりそうだったので、
以前から気になっていたフローチャートの書き方を学んでみることにしました。
フローチャートを学ぶ
フローチャートの基本的な書き方は、
『アルゴリズムをはじめよう』(伊藤静香 インプレス社 2012年)
で学びました。
|
|

Lukia
アルゴリズムというと、コンピューターの世界だけの難しそうなもの。という印象がありましたが、
実はアルゴリズムは、世の中にあふれかえっています。
たとえば、楽譜やレシピ、マニュアルなど。
書いてある通りの手順を踏むことで再現性が担保されるものはみな、アルゴリズムなんだそうです。
フローチャートを自分流にアレンジ。
以下の写真は、私が作ったフローチャートです。

A4ノートに見開きで作っていますが、それでもスペースはギリギリです。
なにしろ紙面の制約があるので、フローチャートのルール通りではないところもあります。
本来、フローチャートは、縦長で下にずらずら〜っと書いていくのですが、
私の場合は、判断の分岐で、上に矢印線が向かっていくこともあります。
フローチャートで用いられる記号は、種類がいろいろあるのですが、
私は、以下の3つだけに絞って使うようにしています。
カプセル型の「開始・終了」記号、
長方形の「処理」記号、
ひし形の「判断(分岐)」記号
また、以下のような独自ルールを設定しました。
「開始・終了」記号は、視認性を高めるため、
開始は一重、終了は二重にすることにしました。
「処理」記号は、には、タスクを書くことがあるので、チェックボックスを書き加えることにしました。
フローチャートが、プロジェクトレベルだと、
いくつかのタスクを内包していることが多いです。
その場合は、「開始・終了」記号のカプセル型と、「処理」記号の長方形を組み合わせた記号によって、
タスク(処理)の開始・終了を表すことにしました。
フローチャートのおかげ。
こうやって、カスタマイズしたフローチャートが書けるようになったおかげで、
これまでよりも、やるべきことがクリアーになったと思います。
そもそもフローチャートは、
実は、意外にも人間以上に複雑な作業が苦手なコンピューターを動かすために書くものなので、
順を追って、シンプルにわかりやすく書く必要があるわけです。
その手法を用いるのですから、モヤモヤさせたままにしておくとか、
その時の流れで、臨機応変にこなす。なんてことは許されません。
最終的に、シリーズ記事を書くためのマニュアルをフローチャート形式で書きたかったのですが、
途中で、その「マニュアル(フローチャート)」を書くためのフローチャートを書いたりしました。
フローチャートが書けるようになったおかげで、
細分化・深化できていなかったところが補えるようになったと思います。
意味のある記号によって文字が囲まれているので、
非常に視認性が高いのもフローチャート最大のメリットだと思います。
少々時間が経ってから見直しても、即流れに沿って作業できますので、学んで損はない表記法ですね。

Lukia
教育職員検定のシリーズ記事にフローチャートをつけようと思います。
どの記事から読めばいいか。などがわかるようにしたいんですよね。
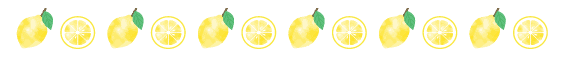 以下の記事一覧に他のボリュームのブログカードを載せています。
以下の記事一覧に他のボリュームのブログカードを載せています。
途中のボリュームからお読みになった方はこちらからどうぞ。
[subscribe2]

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01eafba5.e8fec6de.03acf48d.1cc4eb39/?me_id=1213310&item_id=15876523&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2015%2F9784844332015.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

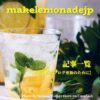








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません