恋人に会えそうな兆しを詠む。
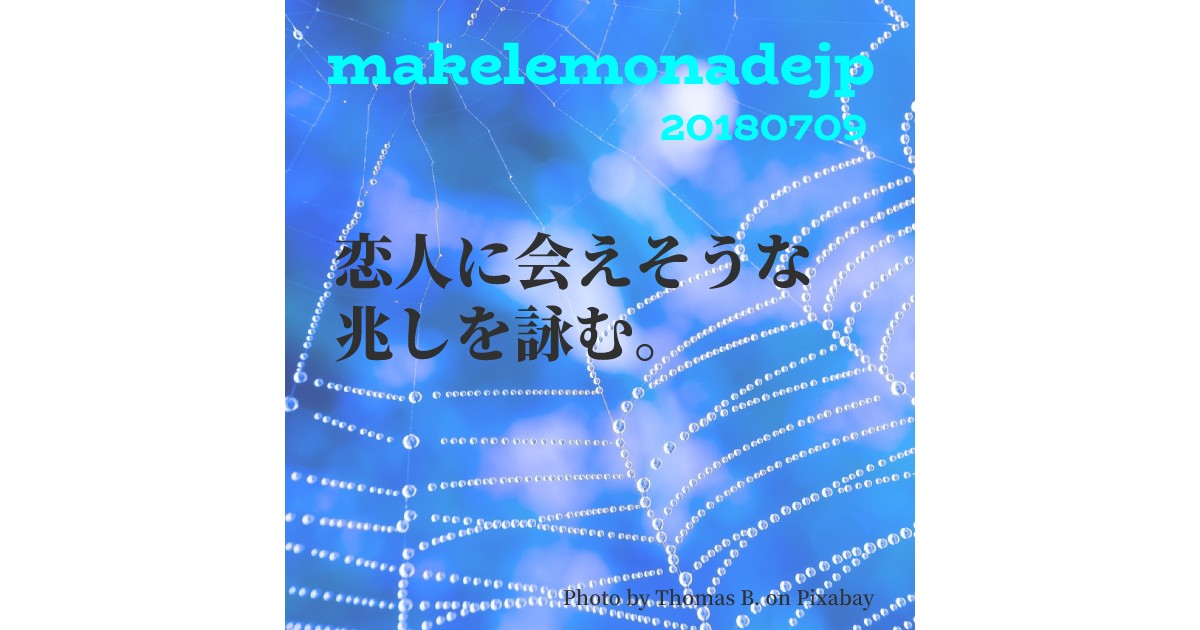
蜘蛛自体は苦手なのですが。
この歌は、ロマンチックで大好きです。
今回も一部だけ品詞分解をしてみようと思います。
歌や作者について
この記事を書くため、久々にネット検索をかけてみると、この歌に関する記事がたくさん出てきました。
どうやら、有名な歌らしいですね。
みなさん、それぞれに知識が豊富なんだなぁ。と、感心させられました。
以下は、その記事を読んで簡単にまとめたものです。
詳しい内容は、元記事のリンクから参照してください。
出典は『古今和歌集』
『古今和歌集』は、我が国初の勅撰和歌集です。
「勅」の字は、「天皇の御命令による」という意味があります。
古今和歌集は、醍醐天皇の命により、当時の代表的歌人、紀友則・紀貫之・凡河内躬恒・壬生忠岑の四人が撰者となり、作られました。
勅撰和歌集を覚えるゴロ
高校時代に習った勅撰和歌集(八代集)を覚えるゴロをいまだに覚えています。
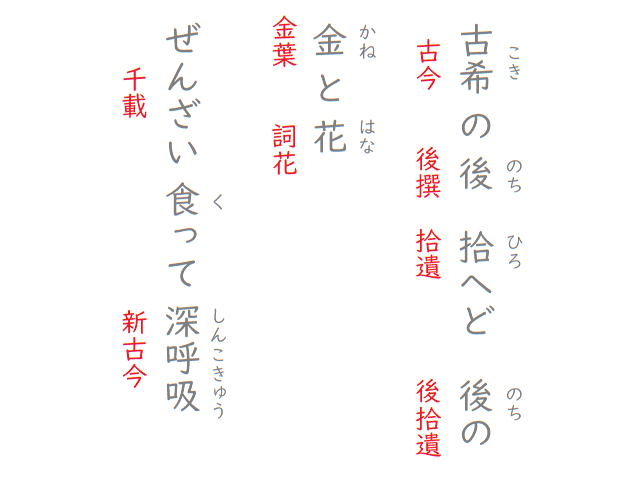
勅撰集は平安時代から室町時代にかけて21種類作られています。
そのうち、古今和歌集から新古今和歌集までを「八代集」と呼びます。
上のゴロに赤字で書いてあるのが、それぞれの和歌集の名前です。
スペースや見た目の関係で、ルビを打てなかったので、以下にそれを示しておきたいと思います。
- 古今和歌集(こきんわかしゅう)
- 後撰和歌集(ごせんわかしゅう)
- 拾遺和歌集(しゅういわかしゅう)
- 後拾遺和歌集(ごしゅういわかしゅう)
- 金葉和歌集(きんようわかしゅう)
- 詞花和歌集(しかわかしゅう)
- 千載和歌集(せんざいわかしゅう)
- 新古今和歌集(しんこきんわかしゅう)
作者について。
作者は、衣通姫です。
変わった名前なのですが、この由来がすごい。
文字通り、何かが衣を通る姫なのですが、その何かとは。
実は、「美しさ」なのです。
衣を通り抜けるほどの美のオーラを持ち合わせているなんて、どんだけ美しいんだ。
美容家IKKOさんが人差し指を振りまくることでしょう。(笑)
美しいゆえの名前であるということは知っていたのですが、
それ以上のことは知りませんでした。
衣通姫は、その美しさゆえ、不幸にもみまわれたのです。
そもそも同性との関係というのは、難しいものですが、
殊、きょうだいとなると、さらに複雑さを増します。
彼女は、第19代允恭天皇の寵妃、または皇女といわれています。
天皇は美しい彼女を愛しました。そしてとうとう、衣通姫は、天皇の正妻であり、自身の実の姉でもある皇后に嫉妬されてしまうのです。
そりゃ~、お姉ちゃんはおもしろくないでしょう。
「私が皇后なのに!」
「あの子は妹なのに!」
身分としても、遺伝子レベルでも、お姉ちゃんは天皇の寵愛を受けてしかるべきなのに、
天皇は、妹ばっかり愛しているのです。
そこで、允恭天皇も策をお立てになりました。
衣通姫を皇居とは別の場所に住まわせて、皇后からお隠しになったのです。

Lukia
天皇が皇居から別の場所にいらっしゃることは、そうたやすくはない。
また、ひんぱんに訪れることもかなわないでしょう。
当時の恋愛は、夜になって、男性が女性のもとをたずねていき、夜が明ける前に帰っていく。というのがルールであったということは知っていたので、
「今晩は彼が来てくれるんだわ。」と心待ちにしている歌だとは思っていましたが、
このような背景があったとすると、衣通姫が天皇を待つ気持ちは、かなり切実なものだったでしょう。
衣通姫について、さらに詳しく知りたい方はは、以下の記事を御参照アレ♪
古今和歌集「わが背子が来べき宵なり」
歌の意味
歌の意味は、およそ次のとおりです。
今宵は、私のいとしい人が訪ねてきてくれそうだ。だって、蜘蛛が活発に糸をかけているんですもの。
「ささがに(の)」について。
旺文社古語辞典によると、
ささがに【細蟹】(名)蜘蛛の異称。小さなかにに似ていることからいう。また、蜘蛛の糸。蜘蛛の巣。「浅茅が露にかかる――」〈源・賢木〉
ささがにの【細蟹の】⦅枕詞⦆「くも」「いと」「い」、またそれらと同音ではじまる語にかかる。(以下略)
ささがねの⦅枕詞⦆「蜘蛛」にかかる。(中略)参考 「ささがねの」は「小竹が根の」と解して枕詞ととらない説もあります。
とありました。
ちなみに、「ささがに」が、「笹が根(ささがね)」から転じた語であることは、下記の記事にも書いてあります。
古語辞典によると、蜘蛛が小さな蟹に似ていることから、「細蟹」となったとありますが、
上記の「浮寝帖」の記事によると、「笹が根(ささがネ)」が、音が似ている「細蟹(ささがニ)」と間違われ、以後蜘蛛を指す言葉として定着したと考えられているといいます。
さっすが、古語辞典。
今回、あらためて古語辞典でも調べてみたら、「ささがねの」についても記載がありました。
もともと、この歌は、『日本書紀』の『允恭紀』に載っていました。

古今和歌集に載っている歌と比べると、違いがあります。
つまり、「ささがねの」とあれば、上代の頃に衣通姫が詠んだ歌で、
「ささがにの」とあれば、平安時代以降に詠みなおされた歌とわかります。

Lukia
結構どうでもいいことなんでしょうけどね。
「来べき宵なり」を品詞分解。

「来べき宵なり」は、上の画像にもあるとおり、「来」「べき」「宵」「なり」と四つに分けられます。
上下の関係を見ながら、品詞分解していきましょう。
「来」
「来」は、現代語なら「来る」です。
これはカ行変格活用という特別な活用です。
古語でも、同じく「カ行変格活用」であることは間違いないのですが、
さて、この活用形はなんでしょうか。また、なんと読めばよいのでしょうか。
それを考えるには、直下にある「べき」が何形に接続するのかがわかればよいことになります。
「べき」は、助動詞「べし」が活用された形であり、「べし」は終止形接続(が上に)の助動詞です。
ゆえに、「来」は終止形です。
カ行変格活用の活用を示すと以下のようになります。
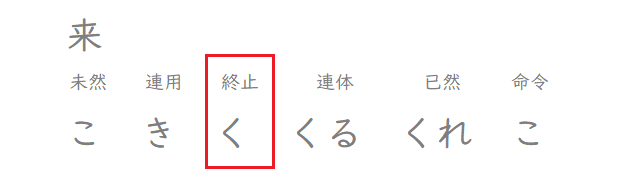
終止形は、「く」と読みます。
ゆえに、「来べき」は、「くべき」と読むことがわかります。
「べき」(宵)
「べき」は、助動詞「べし」が活用された形です。
今回は、活用形が何かだけを考えてみましょう。
そのためには、直下の「宵」との関係を考える必要があります。
「宵」は名詞、すなわち体言です。
下に(連)体言がくることから、「べき」は、「連体形」です。
(宵)「なり」(。)
では、最後の「なり」について考えてみましょう。
「なり」の識別は、古典文法でも頻出の問題です。
詳しいことは、別の記事であらためるとして、今回は、直下と直上の関係から絞り込んでいきましょう。
まず、歌の意訳を参考にすると、この歌は、「我が背子が来べき宵なり」と「ささがにの蜘蛛のふるまひかねてしるしも」と二つに分ける(区切る)ことができます。
つまり、無理やりですが、「来べき宵なり。」と句点(。)をつけることができるのです。
句点(。)をつけられるということは、「なり」が「終止形」であることがわかります。
ここで、動詞の「なる」の活用形の可能性は消えます。
また、直上の「宵」との関係をみていくと、
上に名詞、すなわち体言があるので、連体形(または体言)接続の助動詞とわかります。
助動詞「なり」には、伝聞推定を表す「なり」と断定を表す「なり」があります。
それでは、この「なり」はどちらの「なり」なのか。

Lukia
伝聞推定の「なり」は、終止形接続であり、連体形(または体言)には接続しません。
ゆえに、この「なり」は、断定(~だ・~である)の意味を表す「なり」だとわかります。
まとめ
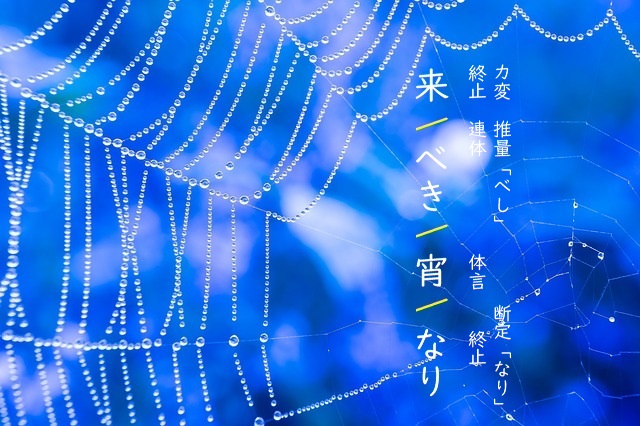

Lukia
もっと速く仕上げられるようになるといいのですが・・・
[subscribe2]









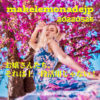
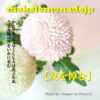
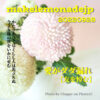
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません