idraft&Google音声入力で、ベタ打ちから解放される!効率的な下書き方法(その2)【ふせんノート2022-2023】

idraftについて
Google ドキュメントを使って、文章を書いたり、「校正」ツールを探したりしたからでしょうか、
ある日、Googleさんにアプリ「idraft」をおすすめされました。
idraft by goo
「goo辞書が作ったテキストエディタで執筆がもっと手軽に、もっと楽しく」
というコンセプトの通り、執筆活動に集中し、執筆作業をはかどらせる工夫がなされたアプリです。
私が特に、いいな。と思っている点は、
「校正」ツール内にある、「表記ゆれ」をチェックしてくれる機能です。
たとえば、文章中に「分かる」と「わかる」とか、「分かって」「わかり」などとあった場合、
「分」に統一するのか、「わ」に統一するのかを確認してくれます。
後で詳しく書きますが、音声入力をしているので、こういう表記ゆれが多発しやすくなるのです。
文章を入力さえすれば、あとで一気に表記ゆれを確認し、修正できるので、
これだけでも idraft を使う意義は十分にあるなと思います。
また、文字数をカウントしてくれる機能があるのもうれしいですね。
1記事あたりの文字数を2000文字程度までにとどめたいと考えているので、
この文字数カウントによって、あらかじめ記事を何分割することになりそうかを知ることができます。
(アイキャッチ画像の枚数が関わってくるので、こういう計算ができるのは大事)
有料のプランもあるのですが、
私の場合は、スマホで使えればいいし、(有料プランはPC版もつかえる)
表記ゆれが直せたらいいので、今のところ無料で十分か と思っています。
goo辞書が作ったアプリなのだから、辞書機能を活用すればいいんでしょうが、
ネットや手持ちの紙の辞典を調べてしまうので、使っていません。
でも、そのおかげで校正ツールが充実しているのでしょうから、頼もしく思っています。
idraft ×Google音声入力=最強?!
校正機能が充実したテキストエディタアプリがほしかったので、
idraft を導入したのですが、
やっぱり、スマホの仮想キーボードでちまちま打つのはめんどくさい。
そこで、ためしに、Google音声入力を使ってみることにしました。
最近は、かなり認識精度が上がっていて、誤字や誤認識は少なくなりました。
マイクのマークをタップして、チカチカしている(反応している)のを確認したら、
ノートに目をやって、ひたすら音読していけばいいので、
入力作業が楽になりました。
また、声に出して読んでみると、文章がわかりやすいか、読みやすい文章になっているかどうかの判断もしやすくなるので、少しまどろっこしく感じた場合は、音声入力の段階で、言い回しや表現を変えるようになりました。
ちなみに、入力時間は、キーボードでベタ打ちしたときとさほど変わらないと思います。
(時短にはなってない)
なんなら、高校3年生からキーボードには慣れ親しんでいますので、(当時はワープロ)
タイピングのスピードは速い方ですし、ブラインドタッチもお手のものなのですが、
長時間、パソコン画面を見つめたり、指を動かし続けるのはしんどくなってきました。
(文字数も半端ないですしね)
脚本や ナレーション原稿を作るように、下書きをていねいに作っておけば、
音読するだけで、すらすら文字化されますので、
編集作業までは キーボードを触らなくていいことになり、
目や手にかかる負担をかなり軽減できていると思います。
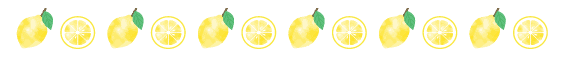
以下の記事一覧に他のボリュームのブログカードを載せています。
途中のボリュームからお読みになった方はこちらからどうぞ。
記事一覧【ふせんノート2022-2023】
[subscribe2]









