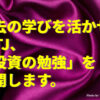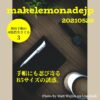戦後生まれにできること:エゴドキュメントを読んで戦争体験をつなぐ
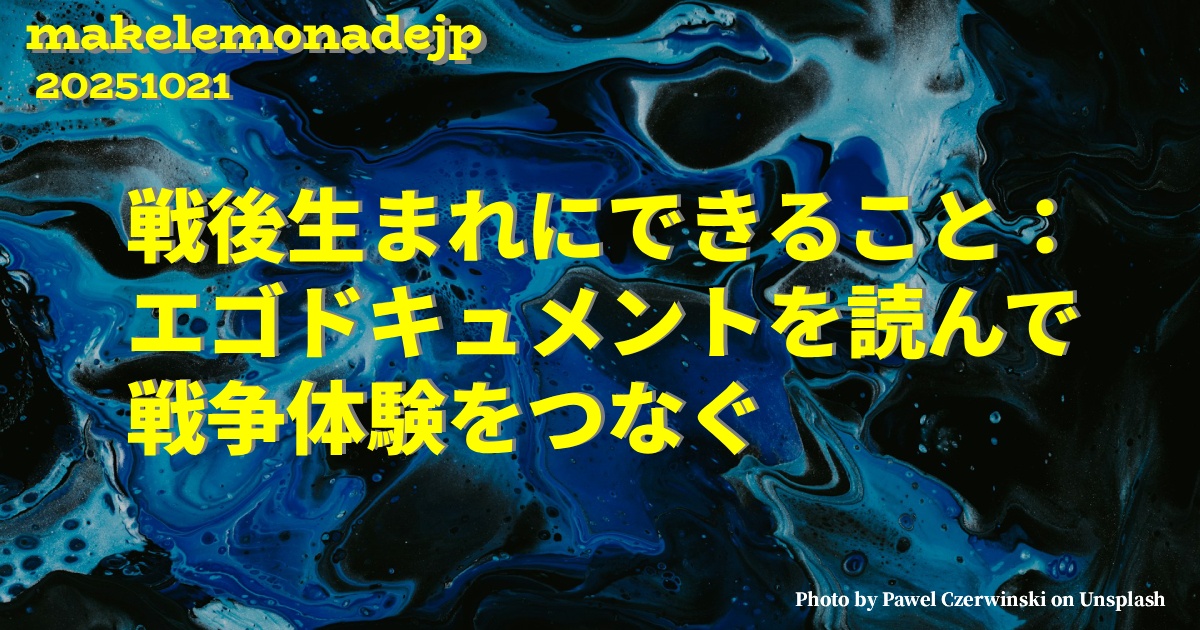
戦後80年の「昭和100年」に思うこと:失われゆく戦争体験を追体験する意味
2025年は戦後80年、そして「昭和100年」といわれた。
二つのメモリアルイヤーが重なったからか、第二次世界大戦に関する番組がたくさん放送されたように思う。
私は、NHKの「新・ドキュメント 太平洋戦争」を見たり、井伏鱒二の『黒い雨』を35年ぶりに読んで、読書感想文を書いたりした。
エゴドキュメントの生々しさを読むにつけ、戦争体験を継承することの難しさと大切さを痛感した。
ちなみに、今年の被爆者の平均年齢は86.13歳だ。
戦後80年というから、その多くが、当時二十歳にも届かない青少年やこどもたちということになる。
ということは、当時、大人であり、生活者であった世代から話を聞くことはおろか、当時、青少年やこどもであった人たちからの体験を聞くことも難しくなっているということだ。
今年、読書感想文を書くため、『黒い雨』を読んだ。
しんどい時間の連続であったけれど、いい体験になったと思う。
それは、主人公重松を通して、大人として、生活者として、あの戦争がどういうものだったのか、戦争をすればどうなるのか、ということをリアルに追体験することができたからだ。
若い世代やこどもは、時代にもよるが、おおむね自決権を持たない。
ということは、大人が戦争を始めたら、否応なく巻き込まれるしかない。
しかし、大人には自決権がある。
自分の家族やその生活を守るため、世論や風潮にどう向き合っていくかを考えることができるのではないか。
誤った時流が、抗えないほどの大きなうねりになる前にできることはないかを考えたり、小さな堰を築いたりするのは、大人にしかできないことだと思う。
戦争体験者や被爆者の高齢化というのは、彼らの体験や経験を年々継承できなくなっていることの表れであり、由々しき事態といえる。
語らずに逝った祖父:若き日のコンプレックスとトラウマ
私の祖父母は、母方の祖母(昭和2年生)を除いて、すでに亡くなっている。
祖父二人、また、父方の祖母からは、結局話を聞くことはなかった。
ちなみに、祖父母は、当時17歳から20歳の若者世代だった。
昔は、「戦争の話を聞いてきましょう」なんて夏休みの宿題があったりしたような気もする。
しかし、祖父母四人から聞き書きしたことはない。
おそらく、一回は聞いてみるも、はぐらかされたり、積極的な応答が得られなかったなどで、以降、聞くのをやめてしまったんだろうと思う。
印象的だったのは、母方の祖父と、戦争に関する施設に行ったときのことだ。
それまでは、歩調を合わせてくれたりしていたのに、何度も姿を消してしまうのだった。
展示はほぼ素通り。所在なげにうろうろするか、足早に去ってしまう。
(ああ、見たくないんだな)と思い、そっとしておいた。
お金も持っているし、携帯電話も持っているから、なんとか連絡はつく。
待ち合わせ場所を伝えて、しばらく別行動にした。
私なりに満足して、待ち合わせ場所に行ってみると、祖父は休憩所にぽつんと座っていた。
戦争に関する展示が何もない、ソフトクリームのポスターなどが並んだ場所を選んでいるようだった。
のんきなパラソルの立つテーブルに座っていたけれど、祖父は周囲の空気を完全に遮断していた。
行ったのは、戦後60年ぐらいだったから、祖父は80歳手前だったと思う。
戦争を知らない私たちの世代にとっては、学びの場所であったけれど、祖父にとっては、つらい記憶が思い起こされる場所だったのかもしれない。
祖父があんなに所在なげにしていたのは、若い頃のコンプレックスやトラウマが蘇ったからではないかと思う。
戦争に関する施設には、若くして散った「ヒーロー」の展示があるものだ。
あの場に行くと、当時の若者は、永遠にあがめたてまつられるヒーローと、そうではない自分という、コンプレックスかトラウマのようなものが心を苛むのかもしれない。
私たちからすれば、戦後をたくましく立派に生き抜いた祖父も、かの「ヒーロー」と同じくすばらしいと思う。
しかし、アイデンティティの確立する若い頃に刻まれた価値観やコンプレックスは、後年他者にどんなに言葉を尽くされても、覆ったり、癒やされたりはしないのだろう。
いつの世も「若者」って複雑なんだな、と思う一件だった。
戦後に始まる新たな「戦い」の中で。
また、父方の祖母は、看護師になりたかったそうだ。
祖父と結婚するまでの間、医院にお手伝いに行っていたらしい。
(今でいうと、看護助手とかナースエイドみたいなものか)
しかし、祖父と結婚し、夫婦の双方にいる若いきょうだいたちの世話や、子供たち(父やそのきょうだい)を生み育てるうち、断念せざるを得なかったらしい。
祖母の葬儀のとき、祖母と十以上ちがう大叔母は、「あんたがいたから、夢をあきらめた」というようなことを言われた。と苦笑いしながら言っていた。
言葉だけを切りとれば、なんともひどい言い草だ。
しかし、二十代前半にして、大家族の主婦となった祖母が、やりどころのない気持を抱えていたことはよくわかる。
当然、祖母自身も自己嫌悪したはずだ。
まだ独り立ちする能力のない幼い妹に、そんなことを言っても。と。
エゴドキュメントの番組や、『黒い雨』を読んで思うが、戦争が怖いのは、日常生活にいつまでもかげを落とすからだ。
他国の人と争うことはなくなっても、今度は「生活」をかけて、同胞といがみ合わねばならない。
最も愛すべき者にも心ないしうちをしてしまうこともあるのだ。
祖父母たちが何も語らぬまま逝ってしまったのは、自責の念やコンプレックスなど、「解決できず、やりすごすしかなかったあのころの自分」を思い出してしまうからだったのかもしれない。
戦後生まれの大人にもできる「戦争体験継承」とは
戦争の話というと、軍人や、最前線で戦った人たちのことが取り上げられるものが多い。
しかし、真の戦争のおそろしさは、日常生活の中にこそあると思う。
同じ年齢代、同じ境遇の人が綴ったエゴドキュメントを読み、自分と対比させてみる。
これが、これからの私ができる、「戦争体験の継承」ではないだろうか。
衣食足りて礼節を知る、ということばがあるように、
衣食住のままならない状態で礼節もへったくれもないのである。
戦争は、わかりやすい波乱万丈ももたらすが、平凡な生活、あたりまえの日常をじわじわと、確実にむしばむのだ。
エゴドキュメントの力:追体験こそが戦争を忌避する心を育む
やっぱり、戦争体験をきいておけばよかったと思うが、
では、来年百歳になる祖母に聞くかというと、聞かないと思う。
80年前のつらさを思い出させる必要性もないし、当時の祖母にもあっただろう、「黒い心」を受けとめる自信もない。
それよりは、できるだけ元気で幸せな時間をすごしてもらいたいと思うばかりだ。
こうしてみると、エゴドキュメントを公開なさる方や、その遺族の方々は、なんとも奇特なことをなさるものだと思う。
『黒い雨』にも、重松やシゲ子たちの手記や日記が含まれている。
これらは、誰かに読ませることを想定していないので、事実やその折に感じたことが、淡々と綴られている。
現実は深刻なのに、そのギャップがかえって、リアルとかグロテスクに感じる。
戦争を忌避する心や考えをもつには、自分と似た境遇の人のエゴドキュメントを読むのがもっとも効果的だと考えている。
その人のエゴドキュメントを読み、万分の一でも追体験すれば、戦争に対して、百害あって一利なしということが自身にしみるのではないか。