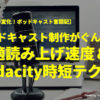「読む・聞く」自在な文章にする3つのポイント【一週間で変化!ポッドキャスト奮闘記】
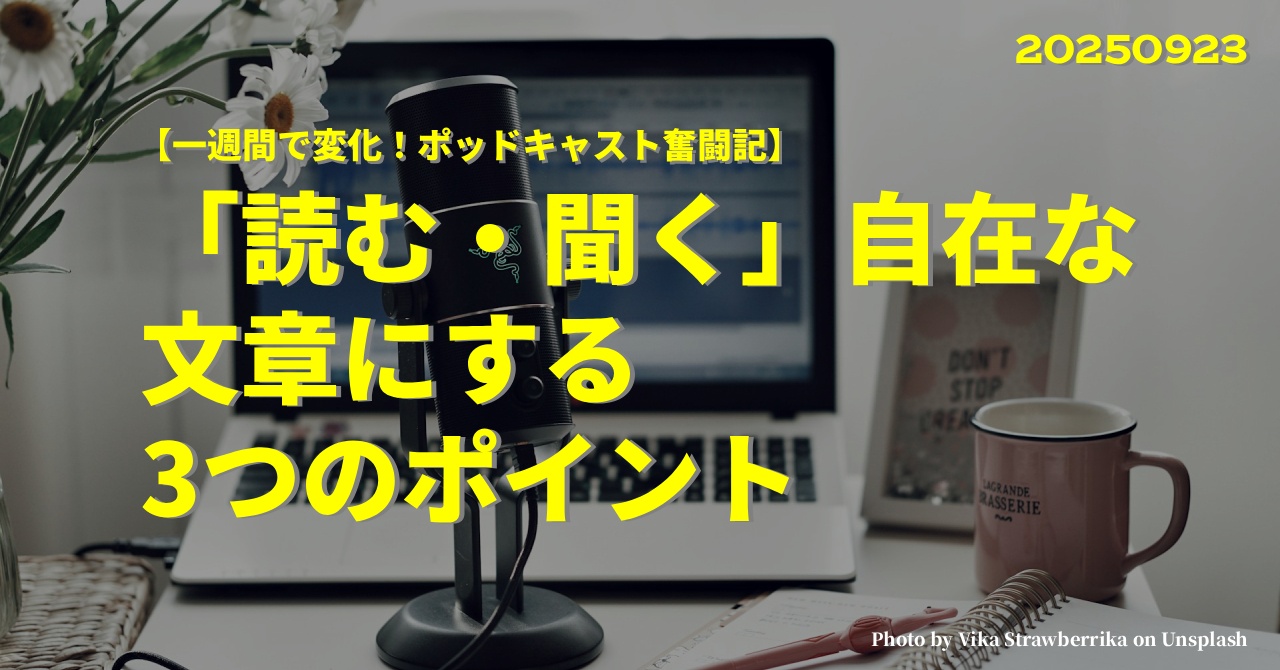
今回は、ポッドキャストを始めたことで得られた思わぬ効果ついて書いてみようと思います。
実は私、記事を音読したことで、文章そのものに、新たな改善点を見出したのです。
一文55字の聞き言葉は、長すぎる?
最初に気づいた改善点は、「一文の長さ」です。
読むとわかる。「一文が長い」と。
これまで、作文指導や文章術のアドバイスとして、「一文は、55字程度におさめよう」と言ってきました。
たしかに、書き言葉、読み言葉としては、適切な文字数なのですが、
読み上げ言葉、聞き言葉としては、一文55字は長いか、長すぎるかもしれない。
とにかく、一文の文字数をもう少し減らそうと思いました。
ちなみに、Perplexityによると、
ニュース原稿の一文の文字数は、45〜50文字以内が一般的とされているそうです。
また、NHKは、一文を50字以内と定めているんだとか。
これは、読み上げにくさが、そのまま聴きにくさや、理解のしにくさにもつながるからだろうと思います。
自分が理解せずに読み上げたものは、当然他者には、もっと伝わりません。
仮に、「リスナーに伝わるのは、読み上げる本人の理解度の八掛けくらい」としてみましょう。
読み上げる人の理解度を\( \ x \ \)とし、リスナーの伝達度、理解度を\( \ y \ \) とします。
\( \ y=0.8x\left( 0<x \leqq 100\right) \ \)
この仮定の式にもとづくと、
読み上げる人が、100%理解していたとしても、
リスナーには、80%しか伝わっていないことになります。
また、読み上げる人が、一文の文字数が長すぎて、その理解度が80%だったら、
リスナーには、64%しか伝わらないことになります。
つまり、長すぎる一文は、発信者とリスナー、それぞれの時間をムダにするということです。
文章を「聞きやすく」するための文字数管理術
そこで、一文を40字程度に収めるようにしました。
Googleドキュメントで、一文の文字数を数えるGASコードを作成し、文字数を意識するようにしました。
ちなみに、GASコードは、一文が41字から50字で文字色がピンク、一文が51字以上で文字色が赤になるように設定しています。
また、私は、原稿を2.5×7.5cmのふせんに書いているのですが、
この段階でも、一文の文字数を意識するようにしています。
最近の私は、ちょっと進化して、小さめの文字が書けるようになりました。
ふせん1枚あたりに、およそ20字程度の文字を書けるようになったのです。(笑)
ですから、ふせんが3枚以上使われた一文は、長すぎることになりますよね。
ふせんの段階で、書き直すことはありませんが、ダブルチェックが利くので、長い一文が減ってきています。
また、長い一文には、接続助詞が使われていることが多いです。
ですから、接続詞を使って、二文に分けるようにしています。
「ストレスなく音読できる文章」にはアレがない
これまで、補足的な要素は、丸括弧( )を使って表していました。
文章の場合は、丸括弧などの記号を読み取れるので、補足的な内容が続くことがわかります。
しかし、音読の場合は、この丸括弧の扱いが難しいんですよね。
「丸括弧、補足説明、丸括弧閉じ」なんて音読するのも、なんかカッコ悪い。
そこで、まず、丸括弧( )自体をなるべく使わないことにしました。
記事によっては、音読音声を収録しないものもありますが、そのことに関係なく、「ストレスなく音読できる文章にしておく」と決めたのです。
丸括弧などの記号が使えなくても、私たちには、「接続詞」があります。
丸括弧( )が使われるのは、たいてい補足説明が必要な場合です。
ですから、「すなわち」などの接続詞を用いることで、丸括弧( )を使わずに済みますね。
読む・聞くに適した文章にするために
自分の記事を音読して気がつきました。
私は、自分が思っていたよりも、聴いて理解するには難しい漢語を多用、もとい、多く使っていたなと思います。
たとえば、「講義」も「抗議」も「広義」も「厚誼」も、「公儀」は、漢語であり、読みはみな、「こうぎ」です。
このように、漢語には、バラエティに富んだ同音異義語があるので、聴いて、理解するのが難しいんですね。
もちろん、聴いていたって、ある程度は文脈で理解できるんでしょうが、
ポッドキャストは「ながら聞き」が前提ですから、文脈を追わない、追えないリスナーがいることも想定しておくべきなんですね。
その点、やまとことばは、漢語ほど同音異義語は多くないですから、やわらかく、平易な表現となりやすいです。
言葉遣いには、人それぞれにクセがあるもの。
そのうち、私のよく使う「漢語」が「やまとことば」になる置換スクリプトを作ろうと思います。
© 2025 Arata Nakahara All Rights Reserved.
<
p style="text-align: center;">