「尽くす」について考え尽くす【友を悼む】

2022年9月27日、
同年7月8日に亡くなった安倍晋三(あべ しんぞう)元内閣総理大臣の国葬儀が執り行われました。
友人代表として、菅義偉(すが よしひで)前内閣総理大臣が追悼の辞を読み上げました。
その追悼の辞にあった山県有朋の歌を解釈してみます。
「尽くす」について調べる
三種類の辞典で調べた理由は、「言葉は生き物」であるという特性があるからです。
山県がこの歌を詠んだのは、今から百十余年前。
言文一致運動などがあっても、知識人の多くは、まだまだ文語体で文章を書いていたような時代であったと考えられます。
まして、山県は、国学を学び、歌を詠む父親から学問の手ほどきを受けているのですから、
彼の脳内にある語彙やその意味は、古語辞典に載っているそれらに近いと思われます。
つまり、解釈の候補にあがっている意味において、
(現代の)国語辞典にあるが、古語辞典にはなければ、
その可能性を打ち消すことができるわけです。
さらに、漢和辞典で、「尽」という文字そのものの意味も調べれば、
古語辞典にある意味を補完・補強することができると考えました。
以下、それぞれの辞典で調べたことを簡略的に示します。
古語辞典「尽くす」
サ行四段活用
① なくする。終わりにする。
② 全部を出す。力を使い果たす。
③ きわめる。その極まで達する。
国語辞典「尽くす」
サ行五段活用
① あるだけのものを全部使ったり、やってみたりする。
② ほかのもののために、力のかぎり努力する。
漢和辞典「尽」
① なくす
② きわめる
辞典的意味からの考察
古語辞典と漢和辞典より、「きわめる」という意味がよさそうです。
伊藤博文の経歴より、国のために力を「尽くし」たと解釈できないでもない。と思いましたが、
これは、国語辞典にはありますが、古語辞典、漢和辞典にはありません。
「尽力」という言葉があることから、自分が持ちうる限りの力を全部出す、使い果たす。という意味はあったでしょうが、「国のために」など 特定の対象にむけて、所有のものを捧げる、奉仕する意味まではなかったと考えます。
(おそらく、言葉が使われるうちに副次的に備わってきた意味であろうと思います)
どちらが「尽くし」たのか
でも、まだまだ安心はできません。
(いや、ほぼ安心していいのですが)
力を捧げる・奉仕するという意味での「尽くす」の可能性をしつこく考えてみます。
実は、歌を知ったばかりのとき、「尽くしし人」の解釈がすんなりできず、
「尽くし(奉仕し)」た人という意味で、2パターン考えていました。
① 伊藤博文が国のために「尽くした」
② 山県有朋が伊藤博文のために「尽くした」
菅前総理の安倍元総理への余りある愛を考えれば、②もありそうだなぁ。と思ったわけです。

Lukia
山県の奉仕の意ではない
辞書を調べた段階で、②は即消去できました。
脳内で、ちょっと山県にちょっとなよっとした言い方をさせてみます。
「あんなに(伊藤に)尽くしたのに、逝ってしまった(そのことがうらめしい)」
「吾は文学の士にならず」と松下村塾入塾の誘いを突っぱねるような武士・陸軍軍人の山県に
こんな依存心があるでしょうか。
「かたりあひて」という言葉があるように、山県と伊藤は自立し、対等な関係性であったはずです。
というわけで、山県の奉仕の意味ではないと判断しました。
伊藤の奉仕の意でもない
では、① 伊藤博文が国のために「尽くした」についても考えてみます。
山県は、「伊藤博文が国のために持てる力を『尽くした』」と考えていることでしょう。
しかし、それを歌の中でわざわざ表す必要もなく、(世の中すべての人がそう考えていたでしょうから)
出し方としても唐突すぎるのです。
「私と語り合って、国のためにその力を尽くした人は、先立ってしまった」
「かたりあひて」と「尽くしし(人)」のつながりがギクシャクしています。
「尽くし」に掛詞のような意味合いがあるのか?とも考えてみましたが、
当時の「尽くす」に「奉仕する」というような意味がない以上、
それもおかしいことになります。
ゆえに、① 伊藤博文が国のために「尽くした」ではないと判断しました。
「尽くした」のは一人じゃない
「奉仕する」意の「尽くす」は、一方的な関係になります。
①なら 伊藤から国へ
②なら 山県から伊藤へ
しかし、この一方的な関係を否定するのが、「かたりあひて」という言葉です。
漢字を充てると、「語り合ひて」となりますね。
伊藤から山県に語りかけるだけでなく、山県から伊藤へも語りかけていることがわかります。
さらに、「かたりあひて」の助詞「て」は、別の動作がつづくことを示しています。

Lukia
「(センバヤマのたぬきを)猟師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ」は、
助詞の「て」があることで、
猟師が、
「鉄砲でたぬきを撃つ」
「たぬきを煮る」
「たぬきを焼く」
「たぬきを食う」
という4つの動作を次々行ったことがわかります。
つまり、山県と伊藤は、互いに語り合い、そして語り合うことに持てる時間や力を「尽くし」たのです。
「尽くし」たのは、一人ではなく、二人であったことがわかります。
会えば必ず話したくなり、ついちょっとのつもりが、時が経つのも忘れ話し込んでしまう。
気がつけば、東の空が明るくなっていたこともあったことでしょう。
時間や気力・体力を尽くすほどたくさん語り合ったのに、
語り尽くして、もはや何も話すことはないなんて思いはみじんも浮かばない。
さっき別れたのに、もう次会ったときに話したいことが頭に浮かんでいる。

Lukia
そして、山県がその懐かしい日々をまざまざと思い起こしているのが、
過去の助動詞「き」でわかります。
これは、直接過去といって、事実や実際にあったことを表現する際に用いられます。
この歌を詠んだ山県の脳裏には、伊藤のさまざまな表情や姿が浮かんでいるのです。
記事一覧
かなり長い記事になりましたので、5回に分けています。
ちょこちょこ読みにきていただければ幸いです。

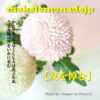

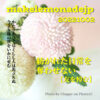
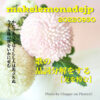
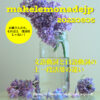


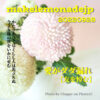

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません