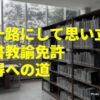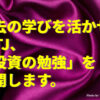「筑紫もち」の包み紙から広がる世界:万葉集から古事記まで
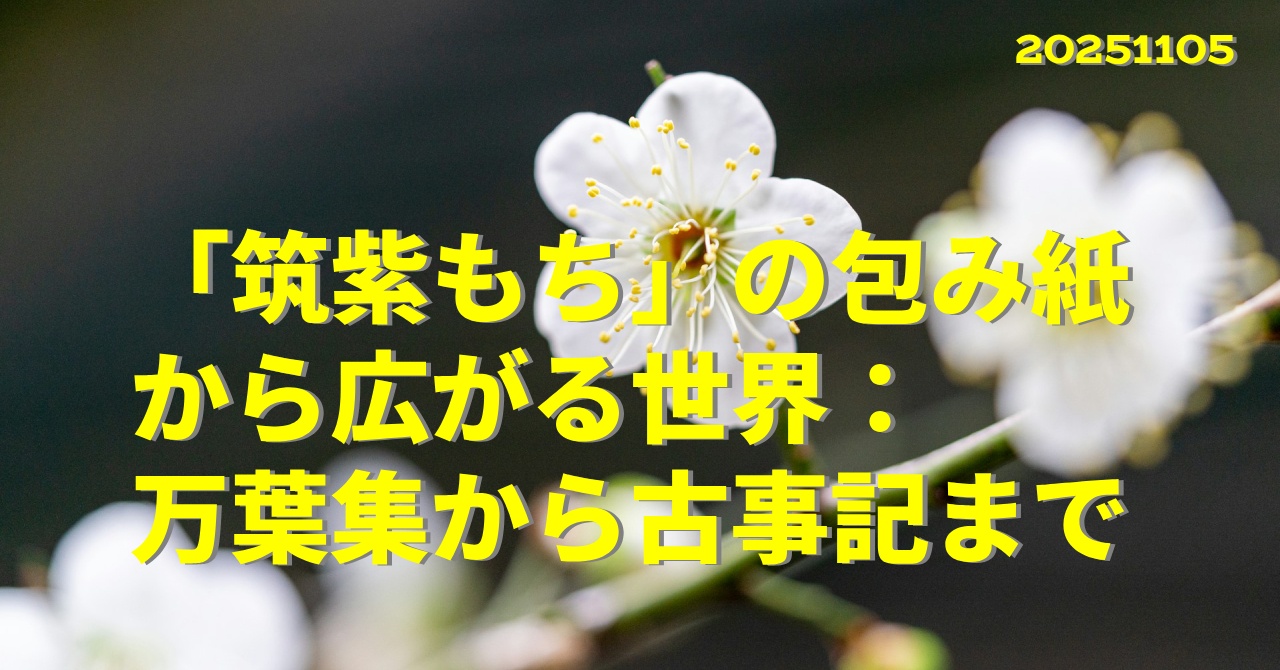
元福岡市民、「筑紫もち」に変体仮名を見つける
姪っ子が、福岡旅行のおみやげに、筑紫もちをくれました。
福岡には、転勤で12年住んでいましたから、お菓子自体は見たことがあり、懐かしく思うのですが、食べたことはありませんでした。
地元民・住民あるあるですね。
地元民・住民あるあるがもう一つ。
「筑紫もち」、私は、「ちくしもち」と読んでいたのですが、公式には「つくしもち」と読むそうです。
ちなみに、福岡県など九州北部では、「ちくし」と読むのが一般的なんだそうで、私も住む間に、その影響を受けたんでしょうね。
ありがたくいただいていると、包み紙に変体仮名を見つけました。
包み紙には、ゴシック体で、歌と、出典、訳までついているという徹底ぶり。
(どうせなら、変体仮名で歌を書いた書家の名も書いておけばいいのに)と思いました。
この徹底ぶりが、お菓子に格調高いイメージを持たせたり、ブランド力を高めるんでしょうね。
包み紙から万葉の世界へ:変体仮名・歌意・作者名を読み解く
さて。
この歌は、万葉集の巻五、「梅花の歌三十二首并せて序」に収められています。
ちなみに、この序文は、元号「令和」の由来となったものです。
三十二首は、815から始まりますので、この歌は、十六番目、まさに中ほどに位置する歌ということになります。
作者は、筑前介佐氏子首です。
筑紫もちの包み紙には、「さしこびと」と書いてありますが、江戸時代前期の国学者、契沖が著した万葉代匠記には、「コカウヘナルヘシ」つまり、「『ここうべ』と読むのであろう」と書いてあります。
これらをあわせて考えると、「さしこびと」なのか「さしここうべ」なのかは、定まっていないのかもしれません。
変体仮名は、私がわかりにくかったところだけを示しておきます。
つまり、今のひらがなに採用されていて、読みやすいものは、省略しています。
よろ徒よにとし者きふともう免の者那たゆ留こと奈くさきわた留へし
よろつよにとしはきふともうめのはなたゆることなくさきわたるへし
訳は、筑紫もちの包み紙に書いてあったものを、そのまま引用いたします。
万代までも年は来ては過ぎ去って行くが、梅の花は、絶えることもなく、きっと咲き続けて行くことであろう。
万葉集の歌で学ぶ!動詞の活用形と助動詞「べし」の7つの意味
この歌で、文法上おさえておきたいのは3カ所あります。
1来経とも
2たゆることなく
3咲きわたるべし
です。
来経は、どう読むのがよいか。
これは、品詞分解するとわかります。
来も経も動詞であることはわかっているという前提で話を進めます。
まず、「来」は、活用形が連用形であることがわかります。なぜなら、直下に、動詞の「経」があるから。
動詞は用言といい、下に用言が連なっているから、連用形なんですね。
「来」が、カ変「来る」なのは問題ないでしょう。
活用は、
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| ズ | テ | 。 | トキ | バ | ! |
| こ | き | く | くる | くれ | こ |
連用形のとき、「き」と読みます。
終止形接続の接続助詞「とも」がありますから、「経」は終止形です。
「経」は、現代なら「経る」といいますね。
これをローマ字にして、erをとると、終止形がわかります。
heru-er=hu
「経」は、「ふ」と読みます。
ちなみに「経」は、ハ行下二段活用の動詞です。
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| ズ | テ | 。 | トキ | バ | ! |
| へ | へ | ふ | ふる | ふれ | へよ |
「たゆる」の活用と活用形は何か?
まず、活用形からかたづけましょう。
「たゆる」の直下に「こと」という体言がありますので、「たゆる」は連体形ということになります。
そして「たゆる」も「経」同様、現代にも同じ語があります。そう「たえる」です。
そして、この「え」は、yeと考えましょう。
ローマ字に直してerをとればいいんでしたよね。
tayeru-er=tayu
終止形は、は、「たゆ」です。
ズをつけると「たえず(た-ye-ず)」となりますから、ヤ行下二段活用ということになります。
「咲きわたるべし」の品詞分解と意味
「咲き」は、直下に動詞「わたる」がありますから、連用形です。
そして、活用はカ行四段活用です。
「わたる」はラ行四段活用動詞ですが、活用形は何でしょう。
活用形は、直下を見ると判断がつくことが多いです。
「わたる」の下には助動詞「べし」がありますね。
「べし」は何形に接続する助動詞かわかりますか?
答えは、終止形接続です。
らむ・らし(ニ) めり・まじ・ベし(ト) なり(アガリ)
で覚えましょう。
そして「べし」の意味は、何かも、考えておきましょう。
全体、歌を読んだら、「咲きわたるのだろう」と推量の意味にとれますが、一応「べし」には、七つの意味があるとされています。
- 推量(咲きわたるだろう)
- 意志(咲きわたろう)
- 可能(咲きわたることができる)
- 当然(咲きわたるのが当然)
- 命令(咲きわたれ!)
- 適当(咲きわたるのがよい)
- 予定(咲きわたるつもりだ)
どう訳すか、どの意味でとるか、というのは、経験値によるところが大きいので、方程式や法則のようにはっきりしたことはいえません。
しかし、「世が続くかぎり、毎年ずーっと、梅の花は咲くんだろうなあ」といっていると考えると、「推量」がよいということになりますね。
契沖はかく解説しき:「萬」と「来経とも」について
ここからは、契沖の万葉代匠記で、この歌に関する記述について。
万葉代匠記は貞享末頃(1688年ごろ?)に成った「初稿本」と、元禄三年(1690年)に成った「精撰本」があります。
この歌だけ
そのどちらでもふれているのが、この歌の「ちょっと変わったところ」です。
初稿本に書いてあることを現代語訳すると、およそ次のとおり。
三十二首のうち、この歌以外は、みな、万葉仮名の一音一字で書いているのに、この歌の「萬世」の「萬」だけは、訓読みの漢字を充てている。どうして、万葉仮名の三字を充てなかったのか。
「萬」は「万」のことです。万代、万世とは、繁栄が長く続くことを示す、おめでたい語です。
契沖は明記していませんが、(佐氏子首は、あえて「万」を書きたかったのでは)と想像していたのではないでしょうか。
契沖の推定を私が推定してみました。
来経とも
ちなみに、精撰本の方は、「この歌だけ『萬』という漢字が使われている」という事実をあっさり記述しているだけなので、省略します。
そのかわり、精撰本の契沖は、「来経とも」にくいついています。
内容はおよそ次のとおり。
古事記で、宮簀姫が日本武尊への返歌としてお詠みになった歌にも、「あらたまのとしがきふればあらたまのつきはきへゆく⋯」とある。
また、この巻下に収録された山上憶良の歌、また第十二のにも「来経」があり、これらはみな、「きふ」と読んでいる。
今回、私たちは品詞分解をして、文法的に、「きふ」と読み取りましたが、契沖は万葉仮名を読んで、解読したようです。
帰還数秒で地雷を踏んだ男:ミヤズヒメ日本最強説
変体仮名も解読できたし、歌の解説もできたし、万葉代匠記までふれられたので、十分満足ではあるのですが、万葉代匠記の精撰本にあった宮簀姫の歌が気になって、調べてみました。
古事記中つ巻の景行天皇九美夜受比売にありました。
ヤマトタケルノミコトが
「天の香具山の上を、鋭くやかましい鳴き声をあげて渡っていく白鳥よ。その姿のように、ひ弱く細い、あなたのしなやかな腕を枕にしようと私はするけれど、(あなたと共寝をしようと私は思うけれど)あなたが着ていらっしゃる襲衣(おすい)の裾に月が出てしまった(月経血がついている)」と詠みかけます。
ぶっちゃけちゃうと、
「え〜、今日、生理なの?じゃ、エッチできないじゃん!」ということ。
「月」とは、月経、月のもの、月のさわり、つまり、生理のことです。
そして、日本で生理は、ケガレと考えられてきました。
初潮を迎えた女の子は祝うのに、その後の生理はケガレだなんて、なんともダブルスタンダードですよね。
しかし、ミヤズヒメもさるもの。黙っちゃいません。
「輝く日の御子よ、統べる力をもつ、我が大君よ、年があらたまり、去ってゆけば、月もまた、来ては去ってゆきます。
まことに、まことに、まことに、あなたを待ちかねている年月のうちに私が身に着けている襲衣(衣、裳)のすそに、月が立たないことがありましょうか。
裳は、成人女性がつける、プリーツ状のスカートのようなものです。十二単では、スカートではなく、トレーンのように変化しています。
ミヤズヒメはカチンと来ているけれど、当意即妙な切り返しをしています。
ざっくりいうと、「帰ってきて、ひとことめがそれ?」という感じでしょうか。
ヤマトタケルはあちこちの平定に出かけて、ミヤズヒメを何か月、もしかしたら何年も待たせているわけです。
ミヤズヒメは、ヤマトタケルが帰ってきたら、その偉業をたたえたりねぎらったりしようと思っていたのでしょう。
そして、逆にヤマトタケルも、待っていた自分をいたわったり、ねぎらったりしてくれるはずだと。
しかし、再会して数秒後、「え〜、今日エッチできないの?」ですよ。
興ざめするし、カチンときますよね。
(感動の再会なのに、エッチのことしか考えてないの?)と。
そして、女性の体のペースやタイミングは、男性の欲求に都合よく合わせられるわけがないのに、ヤマトタケルノミコトが自分本位にがっかりしていることにも腹を立てているのでしょう。
ミヤズヒメは、自分の体のことですから、生理かそうでないかはわかっています。
(おそらく、そのときは生理中ではなかったのでしょう)
見ればたしかに裳の裾に血がついているけれど、それは、茶黒く変色しており、最近ついたものではないことがわかる。
彼を待つ間にやってきた、いつの生理の血かわからないのに、彼は、「えっ、今日、生理なの?」と言いやがる。
外じゃ強いかもしれないけど、女心のわからないへっぽこさ、デリカシーのなさに、ミヤズヒメは、二重、三重で怒っているのでしょう。
「そりゃー、こんだけ待たされれば、生理だって来るよ。何か文句でも?」
つまり、ミヤズヒメは、返歌を通じて、ヤマトタケルノミコトにガッツリ、メンチを切る⋯もとい、凄んでいるのです。(笑)
各地を平定した、さしものヤマトタケルノミコトでも、さすがに「いえ⋯⋯」と、すごすご、しゅーんとしてしまったのではないでしょうか。
こうしてみると、ヤマトタルノミコトをやりこめたのですから、ミヤズヒメこそが日本最強の人物だったのかもしれません。(笑)
© 2025 Arata Nakahara All Rights Reserved.