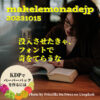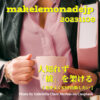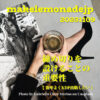原稿テンプレートは育てるもの【KDPでペーパーバックを作るには】

自分仕様のテンプレートを作る
KDP出版に興味がある人は、
何冊か出版したいと考えているでしょうから、
テンプレートを作って、出版を重ねながら育てていくのがよいでしょう。
ページ設定をしておこう
ペーパーバック出版時の見た目を設定します。
用紙サイズ
余白
ヘッダー・フッターの有無や位置
ページ番号の位置、開始番号
フォントの種類・サイズ、(見出し1、見出し2、見出し3ぐらいまでと本文)
概要が表示されるように設定する
以上の項目は、仮設定レベルで作っておきましょう。
ページ番号は、フッターに挿入することが多いでしょうから、
フッターの位置だけは決めておくとよいと思います。
原稿の文字が埋まってくると、この見た目も少しずつ変化していきますので、
都度、細かい修正を加えるようにしておくと便利です。
「概要」というのは、見出しを表示してくれる機能です。
Googleドキュメントでは、
「表示」>「概要を表示」にチェックを入れたら、チェックを外さないかぎり、どの文書でも概要が表示されるようになります。
設定してあると便利な内容
「ページ設定」で見た目の設定をしました。
次に、内容としてあらかじめ作っておきたいもののリストを示します。
はじめに(見出し1か2で)
目次(リンクタイプ)
タイトル(見出し2〜3で)
おわりに(見出し1か2で)
上記の4つは、本として必要なものだろうと思います。
すなわち、毎回書かねばならないものなので、テンプレートにしておけば楽ですよね。
あとは「おわりに」以降に、
著者フォローのお願いをする文とか、
奥付
著者プロフィールなど、
比較的固定的なものも書いておくとよいでしょう。
テンプレートで自分らしさを出す
出版を重ねるうちに、このテンプレートも育っていきます。
ある程度育ってしまえば、テンプレートをコピーするだけで、
いきなり原稿執筆に取り掛かれるようになりますよね。
私も、ブログを運営して5年目になりましたが、
やっぱり、テンプレートを作ったことで、公開までの作業が早くなりましたし、
徐々に億劫さも低減していきました。
一から作らなくていいから、書きたいことを思いつきさえすれば、
それほど時間をかけずに記事が公開できるようになったからです。

Lukia
また、ひとつのテンプレートを基にして、
さまざまな本を作れば、ペーパーバックとしての統一感も生まれます。
表紙や内容は違っても、本文の見た目に統一感があれば、
その人らしさが感じられそうですよね。

Lukia
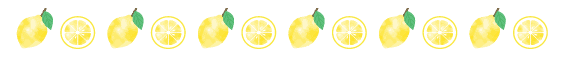
以下の記事一覧に他のボリュームのブログカードを載せています。
途中のボリュームからお読みになった方はこちらからどうぞ。
[subscribe2]